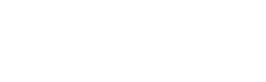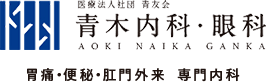投稿日:2025.11.03 最終更新日:2025.11.06
【医師監修】運動不足は「大腸がんになりやすい」はホント?院長が対策まで解説

デスクワーク中心の生活で「若い頃と比べて体型が変わってきた」「毎年の健康診断が怖い…」など、健康に不安をお持ちの方は多いのではないでしょうか。
実は運動不足の状態が続くと、大腸がんのリスクを約30%も高くなってしまうことが研究で明らかになっています。
この記事では、消化器内視鏡専門医の監修のもと、運動不足と大腸がんの関係を解説します。
- 運動不足が大腸がんのリスクを高める3つの医学的理由
- 今日から無理なく始められるウォーキングの実践法
- 当院長がプロデュースした医療発想の足袋シューズ「U×WALK」
- 大腸がんの不安を解消するために本当に必要なこと
青木内科・眼科 青木 洋一郎
総合内科専門医/日本消化器病学会専門医/日本内視鏡学会専門医。日本人の2人に1人が「がんになる」と言われる時代に、早期発見の重要性を知ってもらいたいという思いから「痛くない内視鏡検査」を確立。
【結論】運動不足は「大腸がんリスク」が高まる
結論からお伝えすると、運動不足は大腸がんのリスクを高めることが明らかになっています。
国立がん研究センターの研究では、最も活動的なグループは最も不活発なグループより結腸がんになる確率が約30%低かったという報告結果があり、活動量が多いほど大腸がん(特に結腸がん)のリスクが低下する傾向が示されています。
世界的にも「身体活動と結腸がんとの関連は確実である」と評価されており、運動習慣の有無が大腸がんリスクに与える影響は明らかです。
出典:『日本消化器病学会雑誌|大腸癌の予防』
なぜ運動不足だと大腸がんになりやすいの?
では、なぜ運動不足が大腸がんのリスクを高めてしまうのでしょうか。これには主に3つの医学的な理由があります。
理由1. 「発がん物質」が流れづらくなるから
運動不足になると、腸の『蠕動(ぜんどう)運動』が鈍くなり、便通が滞りがちになります。蠕動運動とは、消化管が波のように収縮して内容物を肛門の方へ送る運動のこと。これは便秘の要因でもあります。
蠕動運動が少なくなると、消化物が腸を抜ける時間が長くなります。それにより食事由来の「発がん性物質」や腸内細菌が作り出す「有害物質」が大腸粘膜と長時間接触することになります。
特に高脂肪食では胆汁酸や分解産物に発がん物質が含まれ、それらが腸内に留まる時間が長いほど大腸の細胞へのダメージリスクが増加するのです。
運動不足に加えて便秘がちな方は特に注意が必要になります。
理由2. 免疫細胞が“不活性化”してしまうから
運動不足の生活では、NK(ナチュラルキラー)細胞などの免疫細胞の活性も鈍くなります。
NK細胞などの免疫細胞は、日々体内に入るウィルスを駆除するはたらきはもちろん、「がん細胞を攻撃するはたらき」もあります。つまり、体内で日々発生する異常細胞(がん細胞予備軍)を排除する力が弱まってしまうということ。
免疫による”見張り”が手薄な状態が続くと、本来であれば免疫系が排除できたはずの異常細胞が増殖してしまい、大腸粘膜でがんに進展するリスクが高まります。
適度な運動はNK細胞の活性化を促し、免疫細胞が全身を巡回してがん細胞を早期に発見・攻撃しやすくなるので、免疫機能の面からも運動は欠かせないのです。
理由3. 肥満や糖尿病になりやすいから
運動不足によってエネルギー消費が低下すると、内臓脂肪型の肥満を引き起こしやすくなります。そして「肥満」そのものが大腸がんのリスク因子であり、とくに男性の大腸がんは“肥満度と相関する”ことがわかっています。
脂肪組織が増えると全身の炎症度がわずかに上昇し(慢性炎症状態)、またインスリンの働きが悪くなることで高インスリン血症(インスリン抵抗性)を招きます。
つまり、がん細胞の増殖を促す格好の土壌が出来上がってしまうというわけです。
他にも肥満体型では腸内で発がん促進物質となる胆汁酸が過剰に分泌される点も指摘されています。
肥満と大腸がんの関係については以下記事で詳しく解説しています。「肥満体型かも…」という方はこちらもご覧ください。

【医師監修】なぜ肥満で大腸がんのリスクが上がるのか?体重増加と癌化のメカニズムを解説
当院でも「私は肥満体型なんですが、癌発症のリスクはありますか?」という質問をよくいただきます。 インターネットで検索しても『肥満の方は癌発症のリスクが高いです』という内容をよく見ると思います。 結論からお伝えすると、肥満は科学的にも大腸がんのリスクを高めることがわかっています。この記事では、がん
大腸がん予防にはどんな運動が良い?
運動が大切なのはわかったけれど、
- 何から始めればいいかわからない…
- そもそもそんな時間は取れない…
という方も多いでしょう。そんな方におすすめしたいのが、特別な準備が不要で日常生活に取り入れやすい「ウォーキング」です。
ウォーキングは、大腸がん予防だけでなく、生活習慣病予防、便秘解消、ストレス解消など、さまざまな健康効果をもたらします。
WHOも週150分以上の中強度運動を推奨していますが、ウォーキングでも十分に達成できます。
“歩行”は質も大切!
「普段デスクワークで座りっぱなし」といっても、通勤や日々の生活もありますので“全く歩かない”という人はほとんどいませんよね。
大切なのは「歩けばいい」というわけではなく、“しっかりと運動レベルになるような質の高い歩行”をすることです。
「1日30分」でOK、少し早めのペースで歩きましょう!
大腸がんを予防する歩き方としては、具体的に1日20〜30分以上を目標に、少し速めのペースで歩くことが効果的です。
少し速めのペースとは、うっすら汗をかき息が上がるが会話ができる程度のペース(Borgスケール:11〜13)、基礎疾患のない方でしたら心拍数110〜120回/分程度が目安です。
ウォーキングは全身の血行を促進し、腸の活性化を促す“腸活に最高な運動”です。歩くときには、顔を上げ、できるだけ背筋を伸ばすことを意識するとさらに良いと思います。
【院長コラム】“歩く”の在るべき姿を矯正する「U×WALK」の開発背景

私は主に消化器内科医として従事しておりますが、「そもそもどうしたら癌患者が減っていくのか」を日々考えてきました。
もちろん、ここまで解説した「歩く」も非常に効果的な予防方法ではあるのですが…、癌の怖さ・予防の意識は実際に患った方にしか芽生にくいことも課題として残っていると考えています。
どうしたら普段から効果的な運動を続けてもらえるか…。
そこで辿り着いたのが、履くだけ“歩き方”が矯正される、「医学目線の歩行専用靴の開発」でした。
「歩き方を忘れた現代人」が、“歩くだけで効果が出る設計”を

私、青木監修の元、メディカル発想の歩行用シューズ『U×WALK』を開発しました。
U×WALKは足袋(たび)形状で足指を自然に広げ、「裸足に近い感覚」で地面を踏めるように設計されている靴です。
足の甲を支えるゴムバンドが、あり履きやすさにもこだわっているのですが、実はそれ以上に、素足で地面を踏んでいるように、地面の感覚をダイレクトに足裏に伝える設計になっています。
足ツボグッズがあるように、足裏を常に刺激することは医学的にも効果的ですが、普段スニーカーや革靴を履いているビジネスマンにとって、地面の感覚(小さな岩やアスファルトのデコボコ)を感じることは少ないでしょう。本来足裏は、歩行の際に必要な多くの情報を脳に伝える感覚器官の役割があります。
この「U×WALK」は、そういった地面からの刺激や重心の移動を感じ、現代人が忘れがちな自らの感覚を使って歩くまさに「医学目線の歩行」に特化した専用靴になるよう設計・開発しました。
“運動不足以外”の大腸がんリスクについて
ここまで運動不足をテーマに解説してきましたが、大腸がんのリスクはそれだけではありません。ここでは、他に注意すべき主要なリスク要因を簡潔にご紹介します。
①:食生活の乱れ
「高脂肪・低食物繊維の食事」は大腸がんリスクが高いと多くの研究で指摘されています。
特にハムやソーセージなどの加工肉に含まれる発色剤(亜硝酸塩など)は発がん性が指摘されているため、大量に摂るのは避けるべきですし、野菜を代表する食物繊維の不足も良くありません。
野菜や穀物に含まれる食物繊維は腸内で発がん物質を吸着して排出する手助けをしますが、不足すると有害物質が腸壁に触れる時間が延びます。
「炭水化物の摂りすぎ」にも要注意!

日本人の主食に欠かせない「白米」や、そのほか小麦類(ラーメン/うどん/パンなど)の過剰接種は、がんの発症リスクを高めます。
そのため、私がよく患者様にアドバイスしているのが、
- ラーメン大盛り➡︎「ラーメン並盛り+野菜盛り」に変更
- カツ丼大盛り➡︎「トンカツ定食(増量+食物繊維の摂取)」に変更
などできるだけ炭水化物を摂取しない小さな工夫です。
もちろん現代の生活で炭水化物をゼロにすることは不可能ですし、栄養バランスを考えずに“食べすぎる”のも問題ではあります。ただ、ついついいつも食べすぎてしまう…という方は、ぜひ上記のような工夫も日々の食事に取り入れていただければと思います。
②:遺伝的要因
大腸がんは生活習慣の影響が大きい病気ですが、直系の家族(両親・兄弟姉妹)に大腸がんの人がいると、平均よりも罹患リスクが高いとされています。
とはいえ、多くの方は遺伝+環境の組み合わせで発症し、家族に患者がいても必ず遺伝するわけではありません。
大腸がんの不安を解消するには検査が必要?
ここまで解説してきたように運動習慣は大腸がんの予防に効果的ですが、それだけで100%防げるわけではありません。本当の意味で安心するために、なぜ専門医が内視鏡検査(大腸カメラ)を強くお勧めするのか、その理由を解説します。
症状がなくても「内視鏡検査(大腸カメラ)」は受けるべき?
答えはYESです。というのも、大腸がんは初期にはほとんど自覚症状がありません。
症状(便に血が混じる、お腹の張り、便通の変化など)が出る頃にはかなり進行している場合も少なくありません。無症状のうちに内視鏡でポリープを取ることで、大腸がんを未然に防ぐことに繋がります。
具体的には、40歳を過ぎたら大腸がん検診(便潜血検査)を毎年受け、発症率が急増する50歳前後になったら症状がなくても一度大腸内視鏡検査を受けることが推奨されます。
実際、大腸がんは男女とも一生のうち約10人に1人がかかる身近な疾患です。
運動や食事で予防に努めてもゼロにはできない以上、プロによるチェックで、できてしまったものは早期に見つけておくのが安心です。
CTコログラフィーと大腸カメラ、どちらが良い?
結論から言えば、大腸内視鏡検査(大腸カメラ)がベストです。
大腸CT検査(いわゆる仮想内視鏡・CTコロノグラフィ)は、腸にガスを入れて膨らませCT撮影し3D画像を作る検査です。
内視鏡を挿入しないで済みますし、検査時間が短いという利点もありますが、あくまでも「大腸CTは内視鏡が難しい場合の代替手段」です。
内視鏡なら直接腸の中を観察できるため診断精度が高く、しかもその場で組織検査やポリープ切除という治療まで可能です。
費用面でも内視鏡と大差なく、どうせ下剤を飲むなら内視鏡までやってしまった方が一度で済みます。
検査を受けるなら安心確実な内視鏡検査を選びましょう。
当院の「痛くない・苦しくない」大腸カメラについて
- 症状は気になるけれど、大腸カメラ(内視鏡検査)はどうしても怖い…
- 過去にやったことがあるけど、痛すぎてもう2度とやりたくない…
などなど、検査への不安が受診への大きなハードルになっている方も少なくないでしょう。
当院では、そもそも「痛くない・苦しくない検査」が行えるよう工夫を行っています。
楽に受けられる3つの工夫
当院では、患者様の負担を最小限にするため、以下の3つの工夫を取り入れています。
1. 鎮静剤の使用で、眠っている間に検査
検査は麻酔を投与して行うため、ほとんどの方が眠っている間に検査が終わり、痛みや不快感を全く感じることなく、リラックスして検査を受けていただけます。
実際に当院で大腸カメラを受けていただいた患者様からも「こんなに楽だとは思わなかった」というお声をいただいています。
2.「軸保持短縮法+水浸法」でお腹の張りを軽減
大腸カメラでよくあるお腹の張り感や痛みは、内視鏡によって腸管が伸ばされた時に感じるものです。
そこで当院では自然なままの腸管の状態で、無理に伸ばすことなく内視鏡を挿入する「軸保持短縮法(じくほじたんしゅくほう)」を採用しています。腸管に無理な力を加えないため、内視鏡挿入時の痛みを大幅に減らすことができます。
加えて当院では大腸内視鏡検査で空気の代わりに少量の水を注入して、腸管をふくらませずに内視鏡スコープを挿入する「水浸法(すいしんほう)」という検査法を行っています。
水を使うことでスコープの滑りが良くなるのはもちろん、腸管を無理に伸ばしたりひねったりする必要がなくなるため、検査時の痛みや検査後の腹部膨満感を大幅に軽減できるのです。
当院では高度な技術と最新の設備により、腸管に負担のかけない「軸保持短縮法+水浸法」を組み合わせ、内視鏡検査の負担を大幅に軽減することが可能となりました。
3.検査準備はご自宅でリラックスしながら
大腸カメラでもっとも大変なのが、下剤を飲んで腸の中をきれいにすることです。当院では、この準備をご自宅で行っていただけます。
事前の診察で、下剤の飲み方や食事の注意点などを詳しくご説明し、専用のキットをお渡しします。リラックスできるご自宅で準備をしてからご来院いただけるため、精神的な負担も少ないと好評です。もちろん、院内にもプライバシーに配慮した専用個室をご用意しており、ご希望に合わせてお選びいただけます。
検査結果を「覚えて帰る」ための工夫
当クリニックでは麻酔検査はもちろん、検査後の「麻酔拮抗薬」も“当クリニック負担”で行っています。
「麻酔あり」で大腸カメラを実施した場合、リカバリー室で休憩後に検査後の説明を行いますが「逆行性健忘(検査前の記憶を思い出せなくなること)」が生じることがあります。
一見すると意識は覚醒しており、会話もしっかりできる状態ですが、あとで「医師からの説明を十分に思い出せない・覚えていない」状態になります。これは麻酔薬の効果が残っている場合に起こります。
しっかりと検査を受け、その結果までしっかり聞いて欲しい。それこそが我々医師の務めだと思い、麻酔拮抗薬の処方までを検査治療として実施しています。
※麻酔拮抗薬は高価かつ保険適応外であるため「当医院の負担」で行います。精神科薬・眠剤を常用されている方には投与できません。
ポリープはその場で日帰り切除できる
検査の際に切除可能なポリープが見つかった場合は、その場で切除(日帰り手術)が可能です。改めて入院する必要がなく、一度の検査で治療まで完了できるため、患者様の身体的・時間的な負担を大きく軽減できます。
大腸カメラで大切なことは、癌化の危険性がある腫瘍性ポリープだけを確実に発見し切除することです。癌化することのないポリープ(非腫瘍性ポリープ)を治療する意義はありません。
大腸カメラは「ポリープを切除したか」で大きく費用が変わります。つまり「ポリープ切除を行ったか」によって患者様のご負担が大きく変わるということです。無駄な治療を行わないことは患者様の経済的なご負担を減らし、医療費を削減することで世界に誇る国民皆保険制度の持続可能性に寄与すると考えています。
腫瘍性ポリープと非腫瘍性ポリープを正確に鑑別し、確実に腫瘍性ポリープのみを切除することは、内視鏡医に求められる必須の技術です。そして、検査あたりの腫瘍性ポリープ発見率(ADR;腺腫発見率)は、内視鏡医が実施する大腸カメラの精度を測る重要な指標とされています。
当クリニックでは「ADR(腺腫発見率)47%」の診察実績を踏まえて、患者様の負担を極限まで減らす大腸カメラ(内視鏡検査)を実施しています。
確かな技術と高い精度の安心な内視鏡検査で、大腸がんで苦しむ方を一人でも減らしたいと心から思っていますので是非お気軽にご相談ください。
米国における2024年推奨値「ADR(腺腫発見率)」:35%
大腸カメラの検査費用はいくら?
症状がある場合や、検診の結果で陽性となった場合の精密検査には、健康保険が適用されます。3割負担の場合の費用目安は以下の通りです。
- 観察のみの場合:5,000円〜7,000円前後
- ポリープを切除した場合:20,000円〜30,000円前後(ポリープの大きさや数によります)
鎮静剤の使用などによる追加費用はいただいておりません。また、ポリープ切除は手術に該当するため、ご加入の医療保険から給付金が受け取れる場合があります。
上記はあくまで目安です。詳細はお気軽にお問い合わせください。
運動習慣と定期的な検査で、大腸がんは予防できます
この記事では、運動不足と大腸がんの関係について解説してきました。
腸の動きの停滞、免疫力の低下、肥満や糖尿病のリスク増加という3つの医学的メカニズムを見てきましたが、いずれも運動習慣で改善できるものです。
この記事のポイントを振り返ってみましょう。
- 運動不足は大腸がんのリスクを約30%高める
- ウォーキングなら生活に取り入れやすく予防効果が期待できる
- 当院長開発の足袋シューズ「U×WALK」で歩行の質を向上
- 運動だけでなく定期検査も不可欠
- 当院の無痛内視鏡なら安心して検査を受けられる
とはいえ、生活習慣の改善だけで完全にリスクをなくせるわけではありません。
当院では、鎮静剤を用いた内視鏡検査で、患者様が「気づいたら終わっていた」と感じるほど苦痛の少ない検査を提供しています。
ポリープが見つかれば、その場で日帰り切除も可能です。この記事を読んで「検査を受けてみよう」と感じたら、お気軽にご相談ください。